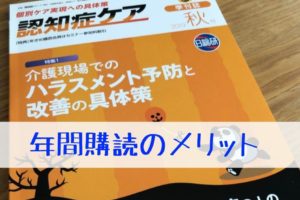「認知症の人の対応が上手くいかない」と言っている人のなかに、「え?上手くいってるじゃん!」と思うことがよくあります。
最近気づいたこと、それは、みんな「認知症に対するケアの結果を高く求めすぎている」ということです。だから辛くなるのではないでしょうか?
今回は、「認知症ケアの目標を高くしすぎるとお互いが辛くなる」ということについて、一緒に考えていきましょう!
キレイな形に収まることを求めすぎてはいないか?
認知症の人の言動について、キレイな形に収まることを求めすぎてはいないでしょうか?
例えば
①「デイサービスなんか行きたくない!」と言っていた人が、「ここに来てよかった!ここのスタッフのおかげで毎日楽しくなった」と言う
とか
②家で家族に暴言を吐いて困らせていた人が、専門職の介入で家族に「ありがとう」と言えるようになる
とか
③施設に入所して「帰りたい!」と怒っていた人が、「ここに居ると安心する」と笑顔で言う
とか
・
・
・
目標高すぎるでしょーーー!!!(笑)

こういう場面が全くないわけではないけれど、こういうシチュエーションを求めすぎてると、いろいろ厳しいと思います。
もっとハードルを下げよう
私がどのように目標設定をしているかというと
「家に帰りたい」と言う人の場合は
“渋々だけど、本当は今すぐ帰りたけど、仕方ないから今日はここに泊まってもいいよ”・・・くらいです。
目標はここで十分です。
他にも
点滴は抜かれるのは3回以内を目指そう
とか
“転ばない”じゃなく、“上手く転ぶ”(ADLが大きく低下するような怪我をしない程度)
とか
私の目標設定はとっても低いです♡

目標を低くするとお互いが楽になる
認知症の人の対応に疲れやすい人は、勝手に期待して裏切られたと落ち込む(苛立つ)傾向が強いように感じます。そういう人は自分にも認知症の人にも厳しく、自分で自分や認知症の人を追い詰めてしまうことがあります。
目標を低くすると、達成できることが多くなり、結果として自己肯定感が上がり、認知症の人にもゆとりを持って接することができるようになります。そうなると認知症の人も追い詰められてる感がなくなり、気持ちが楽になってくるのではないでしょうか。

まとめ
いつも書いているように、介護する側が楽であることがやはり大切なポイントだと私は思います。そこが投影されて認知症に人も楽になるはずです。ゆるらく認知症ケアで好循環のケアを目指して行きましょう!