前回の記事で、「丸く収めようとしなくて大丈夫」と書きました。共感してくれる人が多く嬉しく思っています!今回は、認知症の人同士の口喧嘩などの場面に専門職はどう関わるか?を考えてみたいと思います。
例えば、こんな場面

を数分おきに何度も隣の利用者に聞き、隣の人が

とちょっと怒る
・・・みたいな場面、ありますよね。
そんなとき、皆さんならどうします?
過去の私は、「マズイ!!」と即座に駆けつけ、話をそらし、やんわり認知症の人をその場から離す・・・みたいなことをやっていました。
でも、これって本当に必要な介入なんだろうか?と思うようになりました。私がとっているこの行動って、認知症の人にとっては超不自然な介入だし、何なら“認知症の人がおかしい”という印象を与えてしまうのでは?と思ったんですよね。

介入しないとどうなるのか
で、まあ、私自身、こういう場面に介入することに疲れたというか(笑)、飽きてきたというか(笑笑)。認知症治療病棟とか、日常茶飯事なわけで、こういう小さな認知症の人同士のトラブル的なことにはスルーするようにしたんです。ただ、見守るだけ。
そうしたらですね、意外にあっさりと終わるんですよ。一時的にギクシャクしたり混乱したりすることもあるけれど、職員が変な介入をするよりはあっさりと収まることがほとんどだったんです。
口喧嘩のようなことがあっても、そのあとしばらくすると何もなかったようにテレビ観てあーでもないこーでもないって話してるわけです。
当たり前なんですが、認知症であってもそこはやっぱり大人なんですよね、ほんと当たり前なんですけど。
暴力の場合
男性同士だと、たまーーーーーーーーにつかみ合いの喧嘩になることもあって、そのときだけはさすがの私も介入します(笑)。といっても、なだめるとかそういうことはせず、怪我をしないように物理的に距離を取るように介入する程度です。
多少のトラブルがあるのが社会
認知症ケアだから、介護サービスだから、といってトラブルを全て排除するというのは不自然な気がします。生きている以上、他者と関わる以上、ストレスは付きもので、それがないと何の刺激もないつまらない人生になってしまうと私は思います。
小さな社会(コミュニティ)
私は、施設も、少人数のデイサービスも、病室も、同じテーブルの席の3人であっても、そこに小さな社会が存在すると思っています。
その社会で起こったことは、本人たちに解決してもらう、くらいの対応でも良いのではないでしょうか?もしかしたら、私たち専門職が勝手に過度な心配をしているだけで、本人たちは解決なんて求めていないかもしれませんので(笑)

まとめ
以前の記事にも書きましたが、「何かする」ことだけがケアではないと私は考えています。本人たちが望んでいないことや、自分たちで収めることができることは介入しないということも大切だと思います。結果、お互いが楽になります。








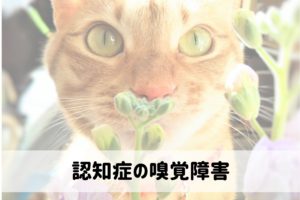













ありがとうございました。参考になりました。