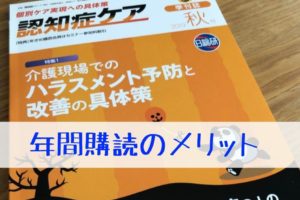摂食・嚥下で「歯」の存在は欠かせないものですが、医療・介護現場では「認知症の人の義歯管理問題」があります。義歯をしていないと思ったら、ポケットから出てきたとか、シーツ交換をしようと思ってシーツを剥がしたら義歯が転がってきた、とか。。。(笑)

また、義歯の紛失は家族からのクレームを受けることも多く、それを避けるために「義歯を外してしまうなら預かって管理しよう」と言う流れになっているところも少なくありません。これは、摂食嚥下の観点からだけでなく、倫理的にも問題があると思います。
今日は、「認知症と義歯」について考えていこうと思います。
認知症だから義歯を外すのか?
まず、根本的に考えたいのはここですよね。認知症だから義歯を外すのか? どう思いますか?
外したもののどうしていいか分からない
認知症の人は、義歯の管理は難しくなってくると思います。なので、口の中が気持ち悪くなって外したものの、どうすれば良いか分からない、という状況があるのではないかと思います。
洗うとか、容器に入れてポリデントにつけるとか、そのあたりは抜けてしまうので、ポケットに入れたり、枕カバーの中にしまったりすると考えられます。
つけていられない理由を伝えられない
義歯をつけていられない何らかの理由があると思われます。
・義歯が擦れて痛い
・義歯が合わなくなり違和感がある
・口内炎がある
など
これを健常者であれば、人に伝えたり、改善するための方法を探すことができますが、認知症の人はこのような理由を適切に伝えることが難しくなります。
逆に言えば、うまく伝えられないから義歯を外すことでSOSサインを出していると見ることもできます。
薬剤の影響
認知症の人は何らかの向精神薬を飲んでいる場合が多いです。
例)
抗認知症薬、抗精神病薬、睡眠薬、抗うつ剤など
このような薬は唾液の分泌を抑えるような副作用があるため、口の中が敏感になり、義歯に違和感を感じるのかもしれません。

義歯をつける時間が短くなればなるほど異物になっていく
私が経験から思うことなんですが、義歯をなくすると困るからという理由で義歯をしないで食事をしたり、食事の時間だけ義歯をつけてもらったりしていると、義歯をしていない時間が長くなるため、そのようなことを続けていると義歯を異物に感じるようになってしまうのではないかと思います。
義歯が命の長さにも関わる
できるだけ長く経口摂取ができるように援助することは専門職としての役割だと私は思っています。
こちらの管理上の問題を優先することによって、結果としてその人が口から食べられる期間を短くし、QOLを低下させ、その延長には命の長さに関わってくる可能性もあるということです。

まとめ
「ショートステイの1週間くらいなら大丈夫だろう・・・」「2週間の入院中だけ・・・」と軽い気持ちで判断しているかもしれませんが、その人の人生を変えてしまうこともあるということを知って、今後のケアに生かしていただけたらともいます。