先日のセミナーでグレーゾーンについて考えるワークを行いました。そのなかで、「もう食べたくない」と言っている利用者に対して、「あと一口頑張って食べましょう」と伝え、その言葉を延々と続けて最後まで食べさせてしまう、ということを話してくれた人がいました。
これも介護現場あるあるですね。私は基本的に「“食べない”と言ったらそこで終了」というスタンスですが、食事量が少ないことに不安を感じる気持ちはよくわかります。
今日は、いろんな側面から、この「あと一口頑張って食べましょう」を考えてみましょう。
「あと一口頑張って食べましょう」
まず、その一口で何キロカロリー摂取できるのか?と問いたい(笑)。そしてこの声かけをしている人で、本当に一口でやめた人を見たことがない。「あと一口」が延々と続く・・・これはどうなんでしょう。。。

完全に嘘ついてますもんね。そう考えると、この声かけって結構色の濃いグレーではないか?と思う。
こういうことが続くと、信頼関係が崩れるので他のケアにも影響が出てしまいます。
「ご飯食べないと元気になりませんよ」
これもよく聞きます。あとは「食べないと点滴になりますよ」もよく聞きます。「完全に脅し」とも思えるこの発言ですが、「ご飯を食べると本当に元気になるのか?」と、これまた問いたい。栄養は確かに大切です。「元気」の定義は人それぞれ違うので、答えはありませんがご飯を食べれば元気になるっていうのはちょっと短絡的な気がします。
身体だけで考えたら、ご飯を食べれば元気になるのかもしれませんが、「人」として考えたら細胞レベルの健康のために、本人の意思を無視されるって、元気とはかけ離れてしまうんじゃないでしょうか。
食べる以外にその人が元気になる方法ってないのでしょうか?

わかっていて選んでいる
「ご飯食べないと元気にならない」なんて、言われなくてもわかっている、という話です。わかっていて「食べない」という選択をしているわけなので、そこを押し切る必要はないのでしょうか?
先ほどの「点滴になっちゃうよ」という発言も、本人にしたら「こんな無理やり食べさせられるくらいなら点滴の方がいい」って感じかもです。
「じゃあ、食べなくていいんですか!?」に対する私のお答え
「じゃあ、食べなくていいんですか!?」という質問が聞こえてきそうですが(笑)。私は、「本人が食べないという選択をしているのなら食べなくていい」と思っていますし、そういうケアをしてきました。
食べないで衰弱していくのを見るのは、不安だし、罪悪感だし、無力感に苛まれる。だから「あと1口」と言いたくなる気持ちはわかるけど、本人が望んでいないなら、それはケアではないと私は考えます。
胃ろうになるのは悪いこと?
「胃ろうになっちゃいますよ」というのもよく聞くけど、それは「胃ろうが良くない」という介護者側の価値観です。
私は、1日3回も辛い時間が来るならば、胃ろうにして楽しい時間を増やす方がずっと人間的ではないかと個人的には思います。
ただ、食べたいけれど口腔領域の障害のために食べられない、という場合は完全に別の対応になります。
まとめ
「食べない」には様々な背景があります。身体的な背景だったり、心理的な背景だったり、認知機能の問題だったり。専門職として様々なアプローチは必要ですが、まずは「本人がそれを望んでいるか?」を確認してほしいと思います。












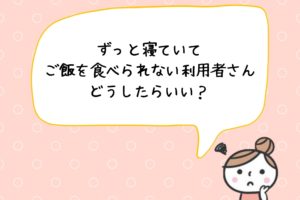

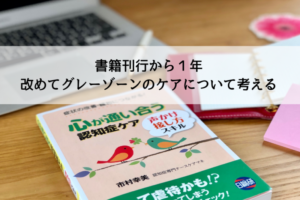








いつもありがとうございます。
自分の中で解答が見えないのが、認知症高齢者の方が何を言おうとされているか、どうしたいと思っておられるか。
言葉を返せない方に色々なアプローチやチームで取り組んでいますがどうもいまひとつ。
しかし、時にはこれもこちらの思い込みかもしないな。と考えるようにしています。