あけましておめでとうございます!

今年もこのブログをどうぞよろしくお願い致します。
昨年最後のブログで、「認知症ケアが変わってきている」と書きました。今日からは、そのブログを受け(ってわけでもないですが笑)私が思う「これからの認知症ケアはこう変わる!」をシリーズでお伝えしていきます。
行動・心理症状(BPSD)への考え方が変わる
今までは「BPSDの対応がうまくなる」ことを求めた
(行動・心理症状(BPSD)に関してはこちらの記事で詳しく書いています)
10年以上前は、「BPSDが出現している人をどうおとなしくさせるか」が主流でした。落ち着かせる、ではなく、おとなしくさせる、です。そこから少しずつ「BPSDには原因がある、原因を探るケア」が生まれて、BPSDを身体抑制や薬で過鎮静にするのではなく、スタッフが上手に対応できるようになろうというケアに変化していきました。
実際は難しい
BPSDの原因を探り、認知症の人が楽になるようにケアをするというのは、とっても良さそうに見えますが、実際は簡単ではありません。ケアがハマると暴れていたのが嘘のように落ち着く人もいますが、そのような方は多くありません。
BPSDが一度出てしまうと、薬を使用しないで症状を改善させることは難しいというのが実際のところです。負のサイクルにはまってしまうと、ずっとお互いにとって苦しい状態が続きます。
これからはBPSDの予防に本気で取り組んでいく
BPSDの対応より、予防のほうがお互いの負担も少なく、現実的だと私は思っています。BPSDの対応を勉強するのではなく、いかにBPSDを予防するか、ここに認知症ケアが楽になるかがかかっていると感じています。
認知機能障害を丁寧にフォローする
BPSDは認知機能障害がベースになります。

認知機能障害は治すことができず、徐々に進行していきます。だからといって、認知機能障害に対して何もしなくていうわけではありません。
認知機能障害へのフォローが大切です。
・記憶障害があってもできるだけ困らないようにする
・見当識障害があっても不安を感じないような環境をつくる
・失行があっても混乱しないようにお手伝いする
とかです。
少しの変化を無視しない
BPSDが出る前って、何らかのサインが出ています。そして、たいていの場合周りの専門職は「なんかおかしいな」「このままだと落ち着かなくなるな」と気づいています。
でも、そこで何もしていないのが多いんです。。。
気づいているのにもったいない!!これからは、その自分の専門職としての感覚を信じてそこで先手を打つことを意識するだけで変わるはずです。
適切に薬に頼る
これは主に介護現場に多いのですが、非薬物療法がいいと思い込みすぎて、「薬を使うことがよくないこと」と錯覚している人がいます。(対応するのが面倒だからといってすぐに薬を飲ませるのは論外です)
「私は見れるから」という理由で、認知症の人が適切な治療を受けることを阻止していないか?と考えていく必要があると思います。
「医者は薬を出すだけ」という先入観を持っている人も多いようですが、そんなことはありません。認知症は医療と介護、両方が必要です。
倫理観をクリーンに
BPSDは専門職のグレーゾーンのケアが引き金になっていることもかなり多いです。全体的なケアをできる限り白に近づけることが、BPSDの予防に1番効果があると私は考えています。
BPSDが予防できれば虐待が少なくなる
新年早々、現実的すぎる内容で申し訳ないですが、医療・介護現場での虐待はグレーも含めたら日常茶飯事です。明らかな「黒」だって、実はたくさんあります。報道されるのは氷山の一角です。BPSDが強い人は対象となりやすいです。
だから、BPSDを予防することに本気で取り組む必要があると思いますし、これから確実にその流れになっていくと思います。
まとめ
シリーズの1回目は、「BPSDの対応」ではなく「BPSDの予防」が主流になっていく、ということをお伝えしました。次回のブログでは「後手から先手へ」ということで介護サービスなどについて考えていこうと思います。




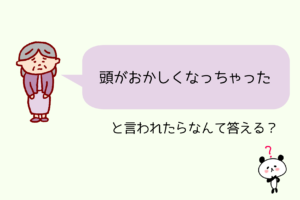


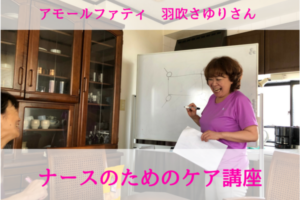












お師匠様
本年もよろしくお願いいたします。
今回のテーマは非常に重くまたやりがいのあるテーマです。
グレーゾーンがBPSDの引き金になていいる。
これは同感です。
何がグレーなのか?個人ではなく、その事業所での共通認識も必要では?
と感じておりますので、今年はこの分野を事業所の社内研修に取り入れるよう
働きかけを行います。
いつも貴重なご指摘をいただき、ありがとうございます。