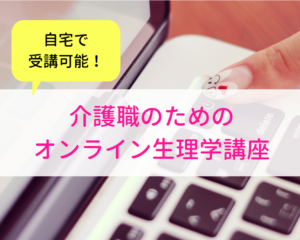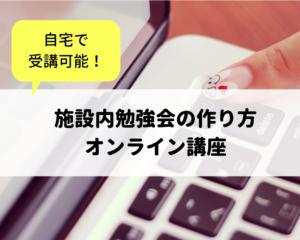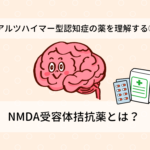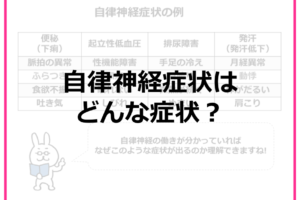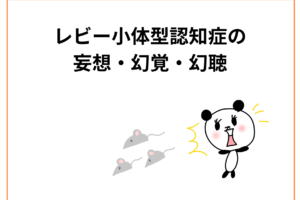「認知症の薬は認知症の進行を遅くする」と聞いたことがあると思います。
抗認知症薬に関しては、メカニズム、効果なども含めてさまざまな研究や意見があります。今後今の薬がこのまま使われ続けるのか、新しい薬が開発されるのかはわかりませんが、しばらくは4種類の薬が主流で進むのではないかと思います。
介護職も「どういう作用なのだろう?」と疑問に思ったことがあるのではないかと思います。
薬理学というのはとても難しい分野ですが、コツコツと生理学や病理学を勉強していけば、ある程度のことは理解できるようになります。
「アリセプトは効かない」「薬を飲んだら余計に拒否が強くなった」と話すのを聞いたことがありますが、ますはメカニズムを理解しましょう。
今日は、抗認知症薬についてお伝えします。
抗認知症薬の種類
抗認知症薬は、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬に分けられ、
アセチルコリンエステラーぜ阻害薬は、ドネぺジル、ガランタミン、リバスチグミンの3種類です。NMDA受容体拮抗薬はメマンチンの1種類です。
アセチルコリンエステラーぜ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬は、作用機序(何に対してどのように働くのか)が違うので、分けて記事にします。
今日はアセチルコリンエステラーゼ阻害薬の説明をします。
正確には「アセチルコリンエステラーゼ阻害薬」なのですが、「コリンエステラーぜ阻害薬」と略して呼ばれることが多いので、ここからはコリンエステラーぜ阻害薬で進めていきます。
商品名
ドネペジル(アリセプト®)
ガランタミン(レミニール®)
リバスチグミン(イクセロンパッチ®・リバスタッチ®)
ドネペジルだけは、ジェネリック薬があります。(ドネペジル塩酸塩)
コリンエステラーゼ阻害薬とは
以前の記事でアルツハイマー型認知症では、コリン作動性ニューロンが障害されるため、認知機能に関係するアセチルコリンの量が減るということを説明しました。
またアセチルコリンを分解するコリンエステラーゼの働きは変わらないため、どんどんアセチルコリンの量が減ることもお伝えしました。
コリンエステラーゼ阻害薬は、アセチルコリンを分解するコリンエステラーゼの働きを妨げる薬です。
コリンエステラーゼの働きを阻害することで、アセチルコリンの量を増やし、認知機能を助ける、ということになります。
コリンエステラーぜ阻害薬は、大きな違いはないので、ここまでの理解でもOKだと思いますが、もう少し深く進めていきましょう。
作用機序
神経伝達物質と受容体
薬のことを理解するのに欠かせないのが、受容体(レセプター)と呼ばれるものです。神経伝達物質については前回も少し触れましたが、もう少し詳しく説明します。
シナプスの末端から神経伝達物質を出します。その神経伝達物質は次のニューロンの受容体と結合することで、情報を伝達します。

受容体は細胞膜の表面に浮かんでいるタンパク質です。神経伝達物質だけではなくホルモンなども受容体と結合することで細胞の内部に情報を伝達します。受容体は、特定の物質とのみ結する構造を持っています。
アセチルコリンの受容体はムスカリン性受容体とニコチン性受容体があります。
健康な脳では、大脳皮質でアセチルコリンが作られ、コリン作動性神経に刺激が伝わると前シナプスからアセチルコリンが放出され、後シナプスのアセチルコリン受容体に結合し、認知機能に関わる情報が伝達されます。
また、シナプスに放出されたアセチルコリンはアセチルコリンエステラーゼやブチリルコリンエステラーゼにより酢酸とコリンに分解され、コリンはシナプス間隙に再取り込みされます。
 ※ACh:アセチルコリン AChE:アセチルコリンエステラーゼ
※ACh:アセチルコリン AChE:アセチルコリンエステラーゼ
ドネペジル
上の図をもう少し簡単にすると、こんな感じです。

ドネペジルは、コリンエステラーゼと結合することでアセチルコリンが分解されるのを邪魔します。
このメカニズムはガランタミン、リバスチグミンも同じです。

ガランタミン
ガランタミンは、コリンエステラーゼを阻害することのほかに、ニコチン性受容体への働きがあります。
アセチルコリンにはムスカリン性受容体とニコチン性受容体という2つの受容体があり、アルツハイマー型認知症の人はニコチン性受容体の働きが悪くなることがわかっているそうです。(ちなみにレビー小体型認知症やパーキンソン病でも同じような変化があるそうです)
先ほど受容体の話をしましたが、いくらアセチルコリンの量が増えても受容体の働き(感受性)が鈍いと物質を取り込んで情報を伝えることができませせん。
ガランタミンはアセチルコリンの量を増やすだけでなく、ニコチン性受容体を刺激し、前シナプスでは、アセチルコリンの放出を増強させ、後シナプスでは受容体の感受性を高める働きがあります。

リバスチグミン
リバスチグミンは、コリンエステラーゼを阻害することのほかに、酵素に対して働きかけます。
アセチルコリンエステラーゼがアセチルコリンを分解するとお伝えしましたが、もうひとつアセチルコリンを分解する酵素があります。それがブチリルコリンエステラーゼです。
リバスチグミンはアセチルコリンエステラーゼだけでなく、ブチリルコリンエステラーゼの活性を阻害し、アセチルコリンが分解されるのを邪魔します。
リバスチグミンはこの2つの酵素を阻害することにより作用を発揮します。

まとめ
「カタカナ多すぎだろー!!!!!」

というお怒りが聞こえてきそうですが・・・笑
今日のまとめです。
1.抗認知症薬はアセチルコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬に分けられる
2.アセチルコリンエステラーゼ阻害薬はアセチルコリンエステラーゼの働きを阻害してアセチルコリンの量を増やす
3.アセチルコリンの量が増える(減るのを抑える)ことにより認知機能を維持することを目的として使われる
次回はNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)について説明します。
◆参考文献はこちらの記事に載せています