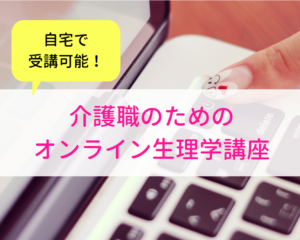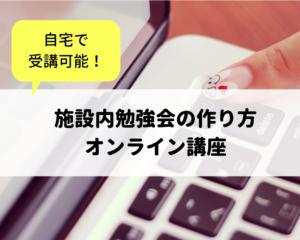前回の記事では、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬についてお伝えしました。今回はNMDA受容体拮抗薬についてお伝えします。
おさらいになりますが、抗認知症薬は、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬に分けられ、アセチルコリンエステラーぜ阻害薬は、ドネぺジル、ガランタミン、リバスチグミンの3種類です。NMDA受容体拮抗薬はメマンチンの1種類です。
NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)とは
メマンチンは、グルタミン酸の受容体を遮断することによって、神経を保護する薬です。
なかなか難しいですよね(苦笑)
コリンエステラーゼ阻害薬よりも、こちらの方がメカニズムは難しいのではないかと私は思います。ひとつずつ読み解いていきましょう。
グルタミン酸
コリンエステラーゼ阻害薬のターゲットはアセチルコリンでしたね。NMDA受容体拮抗薬はターゲットが違います。NMDA受容体拮抗薬のターゲットはグルタミン酸です。
グルタミン酸は、神経伝達物質のひとつで記憶・学習などの認知機能に関与しています。
神経伝達物質は、後続ニューロンを興奮させる「興奮性」と、抑制させる「抑制性」があります。グルタミン酸は興奮性の神経伝達物質です。
アセチルコリンやドーパミンなども興奮系です。抑制系の代表はGABAです。GABA入りのチョコレートが何の効果があるのか、これでわかりますよね!
グルタミン酸が過剰になる
通常、神経伝達が終わったグルタミン酸はすぐに吸収・代謝されていきます。しかし、このシステムに何らかの障害が起こるとグルタミン酸が除去されず、シナプスの周囲に残ります。
グルタミン酸は、興奮性の神経伝達物質なので神経の興奮が過度に続いてしまいます。それにより神経に無駄なノイズが入り、記憶などの重要な情報の信号(シグナル)を隠してしまい、記憶などの認知機能が障害されると考えられています。
グルタミン酸が取り除かれず細胞の外に多く残ってしまうとニューロンが過剰に興奮し、それが長く続くと結果として細胞が死んでしまうということになります。
細胞内にカルシウムイオンが過剰に流入することで,神経細胞が傷害されると言われています。
作用機序
受容体
少し難しくなるのですが、グルタミン酸の受容体はイオンチャネル型と代謝型があります。NMDA型受容体はイオンチャネル型のひとつで、グルタミン酸と結合することで、構造を変えイオンチャネルを開き膜電位を発生させます。
イオンチャネルとは、あらゆる細胞膜にある細胞の内と外の情報をやり取りするためのタンパク質の細い孔(穴)ことで、超高速でナトリウムやカリウムなどのイオンが移動しています。
もう一度、こちらを思い出して下さい。
↓

NMDA受容体は、グルタミン酸が結合することで活性化されます。

どのように作用するか
アルツハイマー型認知症では、過剰なタンパク質の蓄積などが原因で(過去の記事を参考にして下さい)、グルタミン酸が過剰に活性化されてしまうため、ここを抑えるのがメマンチンになります。
メマンチンは自らがNMDA受容体に結合することで、過度な神経の興奮を阻害し神経細胞に対する毒性や細胞の死滅を防ぐ効果があります。

メマンチンのすごいところは、正常な神経伝達時には受容体から離れるという特徴があることです!神経伝達シグナルがうまく伝わることで,記憶・学習機能障害も抑制されると考えられています。
コリンエステラーゼ阻害薬の併用はできませんが、コリンエステラーゼ阻害薬とメマンチンの併用ができるのは作用機序が全然違うからです。
まとめ
1.メマンチンはグルタミン酸の受容体を遮断することによって神経を保護する
2.記憶・学習などの認知機能に関係するグルタミン酸が過剰になると神経毒性をもつ
3.メマンチンはNMDA受容体に結合し細胞の死滅を防ぐ
結構難しいですよねー。(実際はイオンチャネルの話なども含めてもっと難しいです・・・)
前回の記事と合わせて読んでいただけると、コリンエステラーゼ阻害薬と今回のNMDA受容体拮抗薬の違いが少しわかってもらえるのではないかと思います。
◆参考文献はこちらの記事に載せています