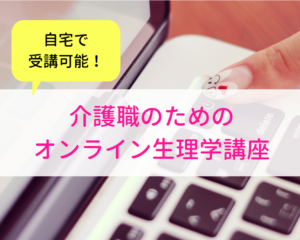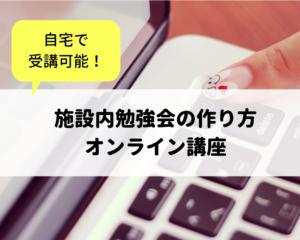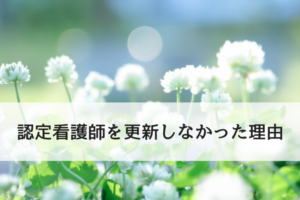こんにちは。ブルーベル代表 市村幸美です。
以前の記事でパーキンソン病とレビー小体型認知症について書いていますが、追記も含改めて整理していきましょう。
レビー小体型認知症の3つのタイプ
レビー小体型認知症のタイプは3つに分けられます。脳幹から病変が現れるものをパーキンソン病、そこから大脳皮質に広がったものを認知症を伴うパーキンソン病、大脳皮質から病変が現れたものをレビー小体型認知症と分けています。(4つに分けている参考書などもあります)
こうやって書くと簡単そうに見えますが、症状が不定形である場合が多く診断は容易ではないそうです。また明確にライン引きできるものでもなく、大脳皮質の病変が先行したレビー小体型認知症でも、数年で脳幹にも病変は広がりパーキンソン症状を伴います。
パーキンソン症状
レビー小体型認知症でよく見られるパーキンソン症状は固縮(筋肉のこわばり)や、無動、動作緩慢、表情の乏しさなどがあげられます。
運動障害でも、骨折などの筋骨格系が原因のものや、脳梗塞などの運動に関わる神経細胞の障害など様々ありますが、レビー小体型認知症やパーキンソン病では、おもに脳幹にレビー小体が蓄積することが原因です。
パーキンソン病の勉強をすると「黒質」とか「線条体」のいう脳の部位が登場すると思うのですが、これは脳の大脳基底核というところにあります。

黒質の神経細胞では運動に関わるドパミンが作られています。正常な脳では黒質で作られたドパミンは大脳の線条体という部位で調整、放出されます。

レビー小体型認知症やパーキンソン病ではこの黒質のドパミンを作る細胞が障害されるとされており、αシヌクレインが原因だと考えられています。
整理すると、こんな感じです ↓
-7.png)
パーキンソン病も認知症と同じで難病でまだ解明されていないことが多い疾患です。
まとめ
1.レビー小体型認知症は3つのタイプに分けられる
2.脳幹にレビー小体が蓄積することでドパミン神経細胞が減少する
3.ドパミンの量が減ることでパーキンソン症状が出る
次はレビー小体型認知症が全身疾患といわれるのはなぜか?ということについて記事にします。
現在募集中のメニュー