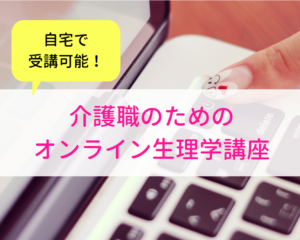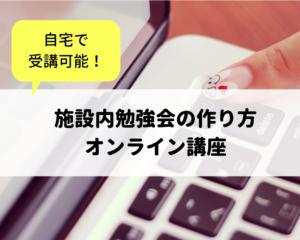こんにちは、ブルーベル代表 市村幸美です。
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症について脳から学ぶシリーズをお伝えしてきました。
2つのタイプをまとめて、改めて脳のことをちゃんとまとめないとなーと思って、とりあえず思いつくことをバーっと付箋に書き出してみたら

結構な数・・・。。。
年内に終われるかな・・・っていうレベル(笑)
リクエストも多いので、頑張ってみます!
・
さて、ずっとブログを読んでくださっていた方は、もしかしたら「市村さん?方向が変わった?」と思ったかもしれません。
以前は、認知症ケアにおける考え方について発信することが多く、そちらの方が反応もよかった感覚はあります。
私が認知症についてブログで発信し始めた頃は、SNSなどで認知症ケアのタブーな部分をオープンに書く人は少なかったので、私はそこを発信するようにしました。

そこから時代が流れて、今は認知症ケアについて発信する人、発信したい人が増えてきました。認知症ケアを語りたい人、語れる人も増えてきました。
認知症ケアの考え方、例えば
・認知症の人に気持ちを理解する
・認知症の人とのコミュニケーション
・認知症ケアにおける倫理観
・・・などなど
これらを発信している方は医療職よりも介護職の方が多く、わかりやすく、そして的を得ていることが多いです。
そのような時代の流れのなかで、私は「今までと同じことを発信していていいのだろうか?」という葛藤が強くなりました。

医療職の私だから発信できること、求められている役割ってなんだろう?と考えてたどり着いたのが、「生理学的な視点でみる認知症ケア」でした。
私自身、本当はこのような生理学的な内容を書く方が好きだったのですが、医者ではない私が書くのはどうなんだろう・・・、ニーズがあるのだろうか・・・、と悩み発信してきませんでした。
ですが、生理学講座をきっかけにからだの仕組みを学びたいと思っている意識の高い介護職さんがたくさんいることを知りました。
ここが後押しになった部分は大きいです。

時間が経過すれば、認知症医療も、認知症ケアも、そして私たちも変化します。
その時々の時代のニーズや、自分が発信したいこと、自分の役割のバランスをみながら、これからも常に動いていきたいと思っています。
では、またー。
現在募集中のメニュー