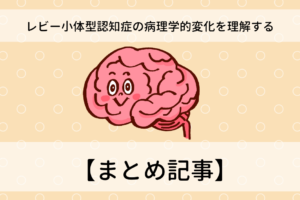こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です。
今日は久しぶりにちゃんとした記事を(笑)
認知症と失語を理解するための基礎知識についてまとめます。失語はコミュニケーションに大きく関わりますので、整理しておくとよいと思います!
認知機能障害と失語
失語とは
認知症の認知機能障害のひとつに失語があります。
失語とは『脳の器質的な障害によって、いったん獲得された言語機能が低下した状態』です。
認知症の定義と似ていますよね。「言語」と「認知」が違うだけ。
もう少し付け足すと、言語は記号の一種で、失語はその記号を扱う能力が低下した状態です。
言語中枢
脳には言語を担当する部位(中枢)があります。
有名なのは
ブローカ野(ブローカ中枢・運動性言語野・運動性言語中枢)
と
ウェルニッケ野(ウェルニッケ中枢・感覚性言語野・感覚性言語中枢)
です

ブローカ野は、発語に必要な筋肉を支配して発語させます。ここが障害されると発語ができなくなります。
ウェルニッケ野は、言語理解に関わります。ここが障害されると言葉の理解ができなくなります。
「聞く中枢」と「話す中枢」は脳の別の場所にある、というこがひとつポイントになります。
ブローカ野とウェルニッケ野は弓状束(きゅうじょうそく)という神経繊維でつながっています。

ブローカ野もウェルニッケ野も大脳皮質です。
認知症との関係
認知症は大脳皮質の神経細胞は死滅する病気です。
認知症になると失語になるのは、これでつながりますね。
「聞く中枢」と「話す中枢」は脳の別の場所にあるということについて、もう少し説明します。
ふだんあまり意識をしていないと思いますが「話す」は運動です。
脳のなかで運動を司るのは前頭葉で、ブローカ野は前頭葉にあります。
「聞く」は感覚です。聞いたことを理解する場所は側頭葉になります。耳の近くなのでなんとなくイメージがつきやすいと思います。

言語中枢は、ほとんどの人は脳の左半球にあります。
ただ左利きの人は右半球にある人もいますし、右半球も言語に関わる機能があるともいわれています。
コミュニケーション
言語的コミュニケーションを考えてみましょう。

相手の話を聞くと、耳から情報(記号)が入ります。
その情報は電気刺激として脳に伝わります。(聴神経を通して神経細胞、神経伝達物質を使いながら情報が伝わり、処理されていきます。)

そして頭頂葉で他の感覚情報などと統合させ、前頭葉で考えて判断します。
ふだん当たり前にできている「耳から入った情報(記号)を理解する」というのも、脳の各エリアが役割を果たし、なおかつしっかり連携が取れているからできることなんですよね。
神経細胞が正常だから、できること。
認知症の人の判断力低下
繰り返しになりますが、認知症は神経細胞が死んでしまう病気です。
認知症になると、判断力が低下しますが、このことがわかれば「そりゃあそうだよねー」ということがわかると思います。
認知症の人の判断力の低下は言語理解だけが原因ではありませんが
視覚・聴覚からの感覚情報を電気刺激で脳に送る際に、その電線である神経細胞が故障しているわけですから、当然エラーが起こります。
頭頂葉はエラーが起こっている情報を統合させ、さらに前頭葉でその情報をもとに判断が下されるわけですから、その場にそぐわない判断をするのはよくわかります。
私は、Wi-Fiが不安定なときのスマートフォンに例えて説明しています。
主な認知症の失語のタイプ
認知症になると、上記の理由からどの種類の認知症でも失語がおこります。
ただ、少し特徴があるので知っておくといいかもしれません。
アルツハイマー型認知症
→喚語困難
喚語とは、「脳の中にある語彙のなかから選ぶこと」で、簡単にいうと言いたい言葉を思い出すことです。
レビー小体型認知症
→会話の反応の遅さ
レビー小体型認知症の場合は、反応は遅くなりますが、内容は理解できていることが多いといわれています。
前頭側頭型認知症
→タイプによりますが、意味性認知症と進行性非流暢性失語では早期から失語が目立ちます。
まとめ
失語は調べれば調べるほど、複雑で難しくわたしもまだまだ理解できていない部分が多いです。
今回は基礎知識ということでまとめました。また勉強してさらに深く説明できるように頑張ります!
では、またー