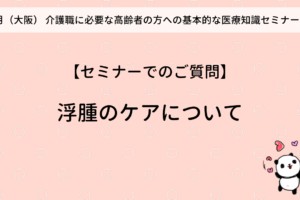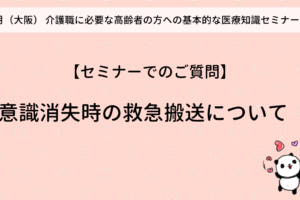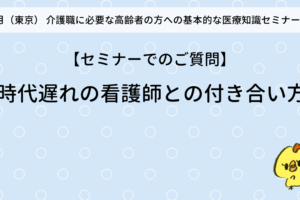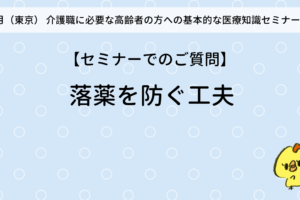こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です
やっと朝でも暖かくなってきたのと、体調が良かったので早朝から五稜郭公園に散歩に行ってきました
あと数日で綺麗に桜が咲きそうです

さて
今日は血圧が低い人に対する下肢挙上についてです。
介護現場では、
常に血圧が低めで、本人に自覚症状はない人に対しても下肢挙上が行われているところがよくあるように感じています
血圧が低い
→とりあえず足あげて寝かせておこう
血圧が低い
→この数値だと入浴させられないから足あげて血圧の数値を上げよう

みたいなの、ありません?
私はやってましたよ(笑)
ただ
全く自覚症状がない人に対しては
「やる必要あるのかな?」
って疑問には思ってました
昔は今のようにすぐにネットで調べればわかる時代ではなかったし
なんの本を読めば答えが載っているのかもわからず、漠然とやってましたよね
私の場合
足を挙げれば心臓に血液が戻ってくるから
って教えられて
なんとなく
「あーそうなんだー」ってわかった気になってた
でも、これだけじゃ説明不足だよね、この先輩(←先輩看護師のせいにする笑)
介護職さんと話していたら、私のように根拠はわからないけど、なんとなく「血圧低い人は足挙げて様子みてます」
って人が多かったのでもう少し生理学の視点から説明をしたいと思います。
知ってる方はスルーしてくださいね
まず基本的なところから

血圧とは
血管にかかる圧力のこと
それでは次
心臓にはこのような法則があります

簡単にいうと
入ってきた分だけ出す
ってイメージ
心臓に戻ってきた血液と同じ量を、心臓の外に送り出す
というのがわかったところで
足を挙げるとどうなるのか?という今日の本題
下肢には約50〜100mlくらいの血液があります
下肢を挙上すると、この血液が心臓に戻ってきますよね

通常は心臓のポンプ機能で血液循環は保たれていますが、追い討ちをかける感じで心臓に戻す感じです
そうすると心臓に戻ってくる量が増えますよね
少し専門的に言うと前負荷が増える、ということになります
で、さっきの法則に当てはめると
心臓に戻ってきた血液の量が増える
↓
心臓から出て行く血液の量が増える
ということになり
結果として、血管にかかる圧力が強くなり
血圧が上がる
ということになります

ここまでOKでしょうか?
これを見ると
「じゃあ血圧低い時は足挙げればいーんじゃん!」
と思うかもしれません
しかし、からだには
からだ(内部環境)を一定に保つホメオスタシスという素晴らしい機能があるため
ある程度のラインに達すると元に戻すようなシステムが働きます
基本的に下肢挙上法はショック状態のときの一時的な処置であって、少し血圧が低めな人に対して行うものではないということです
そして下肢挙上法の研究は少なく、科学的なエビデンスは乏しいといわれています。
効果の時間に関しては、参考文献を2つ提示した上でこのように書かれていました
『この2つの文献を見ても受動的下肢挙上の血圧上昇(心拍出量)の効果は約7分しか得られず、あくまで下肢挙上法は初期の一時的な対応であることがうかがえる。』
【文献】
エキスパートナース 2019年5月号『日常ケアのいまさら聞けない20のこと③ショックが起きたら、まず下肢挙上?』(p21~23)

↑この雑誌です
7分ですって。。。

だらだら寝かせていても、なんの意味もないってことですよね。。。
あと、私も教えてもらうまで知らなかったんですけど
うっ血性心不全の人や肥満の人には下肢挙上法って禁忌だし
他のケースでも下肢挙上することで唾液などを誤嚥して肺炎になるリスクとかも高いそうです
個々のケースによって、じゃあどうするの?ってことは変わってくると思いますが
血圧が低くても本人が全く自覚症状がなかったり
ベースの血圧が低めな方に対して
入浴の基準をクリアするために無理に寝かせて足を挙げる・・・みたいなことは
今後考えて行く必要がありそうですね

「生理学講座、もうやらないんですか」というお問い合わせを、ときどき頂くんですが、今年の10月に開催したいと思ってます。
結局、ここがベースになるなーと思うので。5人くらいの少人数制になると思いますが(笑)
では、またーー