こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です
前回の記事ではせん妄の基礎知識をまとめました
この2つの記事を書くのに50時間くらいかかりました汗 途中から「いったい何をやってるんだ・・・?これ、終わるのか?」みたいな気持ちになってました笑
・
さて2回目の今日は
認知症とせん妄が併発しているケース
についてまとめていきます
前回の記事でも触れましたが、一般病棟等では認知症とせん妄の鑑別が重要になってきます。
では認知症がある人はせん妄はないのか?
と少し混乱しませんか?
私は最初の頃、かなり混乱しました・・・

いろいろ勉強して私なりに理解できた部分があるのですが、それがなかなか言語化できませんでした
今もわかりやすいように説明するのは難しいと感じているのですが、がんばってみますね
・
認知症とせん妄の関係
認知症は代表的な準備因子
前回の記事で書いたように、認知症は準備因子の代表的なものになります
ですので認知症をもっているという時点でせん妄を引き起こしやすいことがわかります

血管性認知症が1番せん妄を併発しやすい
一般的に認知症のなかでも血管性認知症の人はとくにせん妄を併発しやすいといわれています
次にレビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症と続きます
せん妄はBPSD?
まず整理しておきたいのは、せん妄はBPSDなのか?という部分です
ちょっと複雑なんですが、前回の認知症の診断基準を思い出して欲しいのですが
こちら ↓

認知症は「せん妄を否定できる」とありますので、せん妄は認知症のBPSDではないということになりそうです
以前はBPSDにせん妄を含めていた参考書などがありましたが、最近はみないような気がします
なので、認知症とせん妄は関係が深いけど、あくまで認知症とせん妄は別の病態である、と認識してからアセスメントするとよいと思います
例えば糖尿病性腎症は、背景としては糖尿病がある事になりますが、糖尿病と腎機能の低下は別病態ですよね? 全然わかりやすくない説明で申し訳ないですがそういうイメージです

せん妄が併発するとBPSDが重度になる
認知症の人は程度の差はあれ、何かしらのBPSDを持っている人が多いです。そこにせん妄が併発するとBPSDが重度になり、改善するのがかなり難しくなります
急にBPSDが出現した、急にBPSDが悪化したという場合は身体疾患をベースにしたせん妄が起こっていることを疑ってみることが大切だと思います
せん妄は全身状態の悪化のサイン
少し難しく感じるかもしれませんが、症状が似ていても認知症が進んだのとせん妄を併発したのとでは全く違います
認知症の進行は脳の器質的な障害によって進んでいくものなので、仕方がない部分があります
しかしせん妄の場合は、ベースが身体疾患(直接因子)になりますので、ケアの方向性が変わります
精神症状や異常行動をすべて認知症のせいにしてしまっていると、身体疾患の悪化を見逃してしまうことになります
以前参加したセミナーでせん妄は身体状態が変化(悪化)していることの兆しだと教えてもらいました
このことから、医療職はもちろんのこと介護職もせん妄について知識を得ておく必要があることがわかりますよね
せん妄を併発しているケースのアセスメント
症状の分析
認知症の認知機能障害は改善することができませんが、せん妄は改善することができます
まずは丁寧にアセスメントしていくことが大切です
せん妄を併発している可能性があるケースをアセスメントする場合、症状のなかの
・どこが認知症の症状なのか
・どこがせん妄なのか
を分析していくことが必要だと思います
具体例
認知症とせん妄を併用しているケースを、事例で考えてみましょう

日中から何となく落ち着かないけど、夕方から夜間にかけて症状が悪化する、というのは認知症ケアではあるあるですよね
おそらく、日中の落ち着かない感じはBPSDだと思います
そして夕方からの大声はせん妄が併発しているのだと思います
何となくアセスメントしてみるとこんな感じ ↓

認知症とせん妄の関連を私なりに考えて図にしてみました

これは私が勝手に考えたもので間違えているかもしれませんので、参考程度にしていただけたらと思います
これは私の推測ですが、まず認知症という準備因子があり、身体的ストレスや心理的ストレス等の誘発因子がある時点で、おそらくBPSDが出現していると思います
軽くこちらも載せておきます ↓

そしてその状態にさらに身体的要因(直接要因)が重なることで、せん妄(意識障害)が起こり、BPSDが悪化していることが考えられると思うんです
せん妄を併発しなかった場合でも身体的ストレスが強くなることで、BPSDは重症化していくはずです
せん妄もBPSDも基本的には介入によって改善する病態ですが、介入が遅れたり不適切だったりすると、症状が固定してしまうような印象があります
BPSDもせん妄も予防が命!
BPSDもせん妄も、正直なところ、症状が出てしまってから沈めるのはかなり難しいです。
BPSDの予防とせん妄のケアは似ています。「当たり前のこと」がちゃんとできているかどうかが重要だと思います。
確かにせん妄の予防は、面倒くさい・・・と思うかもしれません。
でも、いろいろな研究からせん妄の予防がわかっているのに、それをやらずにせん妄を引き起こし、「せん妄だから手がかかって困るわ」というのは何だか矛盾しているように感じます
改めてせん妄を予防するためのケアを確認していきましょう
せん妄の予防

基本的なことばかりですが、このようなケアを丁寧にできていることがせん妄の予防につながります
面倒だなと思うかもしれませんが、せん妄が起こってしまったらケアはもっともっと大変になりますし、事故のリスクもグンと上がります
せん妄が疑われる場合は、脱水などの身体症状はないか?せん妄を引き起こしやすい薬剤を服用していないか?などを改めて再確認してみるとよいと思います
オピオイドのような薬剤を使用している場合は、せん妄があるからといってその薬を中止するというのは難しいと思いますが、中止や変更が可能な薬剤がある場合もあります
そのためにはせん妄の可能性に気づき、できるだけはやく医師に相談することが大切だと考えています
認知症とせん妄を併用しているケースの目指す方向性
認知症がない場合はせん妄が改善すれば元の状態になりますが、そもそも認知症がある場合はせん妄がなくなっても正常な状態に戻らないということはわかりますよね
ですので私が思うケアの方向性は
せん妄を改善してBPSDを軽くする
と言うのが現実的かなと思います
1+1=2
の状態を
1+0=1
の状態にするイメージですかね
理論上、ケアによっては0+0=0にすることも可能だと思うのですが、高齢で認知症があって何らかの身体疾患をもっているのであればBPSDを全く0(ゼロ)の状態にすることは難しいと思いますし、そこまで求める必要もないのではないかと思います
認知症があれば多少のBPSDはあって当たり前、と思っておいたほうがお互いに楽なような気がします
BPSDがあっても可能な限り本人の不安や苦痛を最小限にする
ここが大切かなと思っています
・
前回の記事と合わせてとっても長い記事になってしまいました・・・
文章にしようとするとなかなかうまく表現できないことが多く、自分でもまだしっかり理解できてないんだなぁということがわかりました
これからまた少しずつ勉強して、わかった事はこちらの記事に追記していきます!
最後まで読んでいただきありがとうございました
では、またーー
↓募集中です!



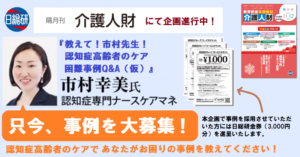 」
」




-2-1-300x200.png)











