こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です
連載の原稿を無事にすべて入稿し、ホッとしている市村です(笑)
オンラインセミナーや動画講座などの依頼が増えてきて、新年度だなーと感じています。

さて今回の記事は嗜銀顆粒性認知症についてです。
昨年長谷川和夫先生が亡くなりましたね。個人的には、遠い親戚が亡くなったときより、ショックでした。
1度ですが講演を聞かせていただいて、本当に感銘を受けたんすよね。ちなみにその講演は長谷川和夫先生と、和光病院の院長である今井幸充先生のコラボで大興奮したのを覚えています。
本当にいろんなことを学ばせていただきましたし、認知症医療やケアを思いっきり引き上げてくださった方だと思います。
本当にありがとうございます。
・
長谷川和夫先生はご自身が認知症になったことを公表されていましたが、その病名が嗜銀顆粒性認知症でした。
聞き馴染みのない病名ですよね。 私自身も何度か参考書で読んだことがありましたが、しっかり勉強したことがなかったので正直「どんな認知症だったっけ?」と思いさせなかったのが正直なところです。
少しわかりにくい用語も出てきますが、興味のある方は読んでみてください。
嗜銀顆粒性認知症(AGD) とは
まず嗜銀顆粒性の読み方ですが「しぎんかりゅうせい」です。嗜銀顆粒性認知症は略してAGDと表記されることもあります
脳内に「嗜銀性顆粒状構造物」が沈着する神経変性疾患です。
この病態を理解するためには、まず「タウオパチー」「タウ蛋白」「嗜銀顆粒」を理解する必要があります。難しいですが、がんばりましょう!

タウオパチーとは
タウオパチーとは,「タウ蛋白が細胞内に蓄積する状態」の総称です。「タウ蛋白」という用語は認知症を勉強した人なら聞いたことがあると思います。
タウ蛋白は、嗜銀顆粒性認知症だけでなくアルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症にも関係しますので、タウ蛋白について確認していきます。
タウ蛋白とは?
タウ蛋白は微小管に結合しています。微小管は細胞内の骨格を保ようなもので、神経細胞の軸索の機能に必要な役割をしています。

そのタウ蛋白が異常になると軸索が変性し、神経細胞が上手く働かなくなってしまいます。

微小管結合部位が 3 カ所のもの(3 リピートタウ)と 4 カ所のもの (4 リピートタウ)があるらしく
3リピートタウが主にたまる疾患→ピック 病
4リピートタウがたまる疾患→嗜銀顆粒性認知症,進行性核上性麻痺,皮質基底核変性症
両者がたまる疾患 → アルツハイマー型認知症
になるんだそうです。
嗜銀顆粒とは
先ほど登場した4リピートタウが異常に蓄積された物質を嗜銀顆粒と呼ぶそうです。1987年にドイツの神経病理学者であったブラーク夫妻が発見されました。
銀染色により紡錘型・コンマ状で描写されていたので、嗜銀顆粒と命名されたんだそうです。
プラーク先生は嗜銀顆粒の存在と、それに伴う変性のみで認知症をきたすケースを「嗜銀顆粒性認知症」と定義しました。
新しい認知症のタイプですね。
病態
病変は迂回回,扁桃核から海馬,側頭葉の内側、前方に進展することがわかっています
・迂回回とは
側頭葉・扁桃核移行部の 脳回で,前部嗅内野とも呼ばれます


画像診断では側頭葉内側面前方の限局性萎縮を認め,左右差を伴うことが特徴のようです。この左右差は MRI のほか SPECT や PET などの機能画像でも確認す ることができるんだそうです。
発症年齢は高い
アルツハイマー型認知症よりもさらに高齢での発症が多いといわれています。
他の神経変性疾患と同様で、進行は緩徐です。
症状
記憶障害がありますが判断力や遂行能力は比較的保たれ認知機能障害は比較的軽度で,ADL も保たれる傾向にあります。
焦燥, 不機嫌,易怒性,易刺激性、自発力低下などの情動面での障害が出現します。
アルツハイマー型認知症よりも認知機能障害は比較的軽度で情緒面の不安定さか症状として現れやすいのかなと言う印象です。
まとめ
レビー小体型認知症よりもさらに新しい認知症のタイプで、未解明な部分も多く文献も少ないですが、ここ数年の医学雑誌ではよくみかけるようになりましたね。
アルツハイマー型認知症と誤診されていることも多いそうです。また新しい情報をゲットしたらシェアしていきますね!
では、またーーー
【参考文献】
嶋田裕之:高齢者タウオパチー(嗜銀顆粒性認知症,神経原線維変化型)の臨床
森 秀生 :1.認知症の病態解明の進歩―認知症と蛋白異常による分類と病態 4)タウ蛋白、日本内科学会雑誌 第100巻 第 9 号
↓募集中です!



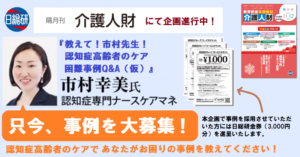 」
」





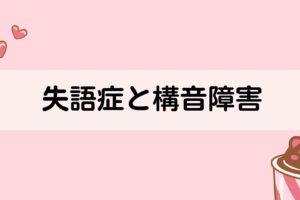


-2-2-300x200.png)







