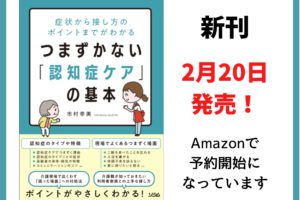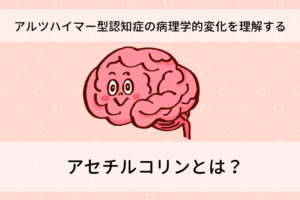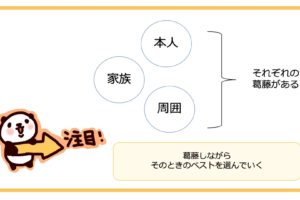こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です。
血管性認知症シリーズは今回で最後になります。
最後は血管性認知症の症状、そしてアルツハイマー型認知症との関係に触れていきます。
血管性認知症の主な症状
記憶障害は軽度
認知機能障害では実行機能障害や注意障害が目立ちます。病変の部位にもよりますが、記憶障害は軽度で理解力や判断力も保たれる場合が多いです。
こちらの記事の「認知症発症に戦略的な部位の単一病変による血管性認知症」の場合は、記憶障害が目立つケースの人もいます。
嚥下障害や麻痺などの神経症状を伴うことが多い
嚥下障害や麻痺などの神経症状を伴います。また構音障害などの言語障害も伴います。

脳卒中の急性期には30〜50%の人に嚥下障害がみられるそうですが、急性期から回復するにつれて改善するケースも多く見られます。(文献によっては70%と書いてあるものもあります)
意識障害をきたすような大脳半球の病変や、脳幹の病変などで嚥下障害が出現します。
参考文献
藤島一郎著:脳卒中患者における嚥下障害の診かたと管理、日本老年医学会雑誌、40巻2号
脳卒中の嚥下障害についてはなかなか難しいので、別の記事でまとめますね。
意欲低下やアパシーがみられる
血管性認知症では抑うつや意欲の低下、アパシーがみられることがあります。判断力は保たれる傾向にありますが、考えるスピードが遅くなるという特徴があります。
パーキンソニズム
血管性パーキンソニズムと呼ばれており、多発性脳梗塞やビンスワンガー病が原因で起こるといわれています。安静時振戦はあまりみられないのが特徴です。
血管性認知症とアルツハイマー型認知症の関係
私が認知症を勉強し始めた頃は、血管性認知症とアルツハイマー型認知症の鑑別をどうするかといった内容の記事をよく読んだ気がします。アルツハイマー型認知症か血管性認知症か、という二者択一の時代。
しかし、今は血管性認知症とアルツハイマー型認知症は併発しているケースがあるという見方が一般的になっています。
高齢者ではアルツハイマー病理(アミロイド沈着など)と小血管病性病変(ラクナ梗塞など)を併せ持つ症例が多いことが、色々な研究でわかってきているようです。
参考サイト
公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ
また昔は「混合型認知症」という用語も使われていましたが、今はあまり使われていません。
アルツハイマー型認知症の診断基準を満たし、脳血管障害もあるケースについては「ADwithCVD(脳血管障害を有するアルツハイマー病)」 と呼ぶことになってきつつあるようです。

参考文献
長田乾、高野大樹、山崎貴史、加藤文太著:血管性認知症の概念の成立と変遷、老年精神医学雑誌、第32巻第10号
・
いかがでしたでしょうか?
いつものことですが私が1番勉強になりました笑
血管性認知症の病態は、4大認知症のなかで1番難しいと感じています。
これからまた新しい 情報が入ってくると思いますので、なるべく新しい情報を更新できるようにしていきます。
では、またーーー
・北川一夫著:高齢者の脳血管性認知症、日本老年医学会雑誌54巻4号
・藤島一郎著:脳卒中患者における嚥下障害の診かたと管理、日本老年医学会雑誌、40巻2号
・長田乾、高野大樹、山崎貴史、加藤文太著:血管性認知症の概念の成立と変遷、老年精神医学雑誌、第32巻第10号
・公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ