認知症とは?
認知症とは?
脳の障害のために、認知機能が失われ、日常生活に支障をきたす状態
脳の障害のために、認知機能が失われ、日常生活に支障をきたす状態
何らかの原因によって脳実質に異常が起こり、もともと脳が担っていた役割を十分に果たすことができなくなることによって、起こる症状を認知症と言います。

脳にはさまざまな役割がありますが、認知症になるとこの役割が果たせなくなってきます。例えば、側頭葉に障害が出ると、記憶に関することに障害が出たり、聞いたことを理解して話すといったことが難しくなります。
認知症の症状
認知症の症状には、脳の障害によって直接起こる認知機能障害と、それに伴って起こる行動・心理症状(BPSD)があります。

認知機能障害とは?
認知機能障害は、種類や進行度によって違いはありますが、認知症になったら必ず出る症状のことを言います。

行動・心理症状(BPSD)とは?
行動・心理症状(BPSD)は、認知症になったからといって必ず出る症状ではなく、先述した認知機能障害を起因とした2次的な症状をさします。個人差が大きく症状に変動があるのが特徴です。

行動・心理症状(BPSD)は、認知症の人の不安や苦痛の表現だといえます。
認知症の種類・経過
認知症にはさまざまな原因があり、原因は70種類以上あるともいわれています。そのなかでも発症の頻度が高い4つの認知症があり、4大認知症とも呼ばれています。

進行や予後は、認知症のタイプによっても違いがありますが、一般的にはゆっくりと進行していきます。
治療
根本的な治療はまだ確立されていません。認知機能障害の進行を遅くする抗認知症病薬、行動・心理症状(BPSD)に対する抗精神病薬などが使用されます。
まとめ
認知症の理解はポイントをおさえれば、さほど難しいものではありません。そして理解してしまえば、認知症の人の不可解な行動を理解しやすくなり、ケアへの視野も広がります。















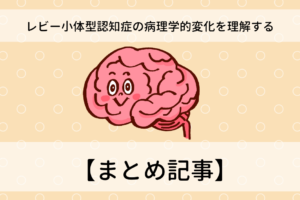
-4-300x200.png)









