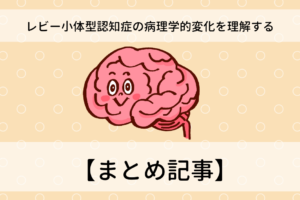認知症の症状は?
認知症の症状は大きく認知機能障害と行動・心理症状に分けられます。認知機能障害は、記憶障害、見当識障害、実行機能障害、失語、失行、失認などです。これらの症状は脳の障害によって直接起こるもので、認知症の種類や時期によって症状や程度の差はありますが、認知症に共通してみられる症状です。認知症の人に見られる妄想や徘徊などの行動・心理症状は突然現れるものではなく、この認知機能障害がベースになっています。

行動・心理症状(BPSD)とは
行動・心理症状(BPSD)は不安、焦燥感などの心理症状や、徘徊や暴力などの行動症状をまとめた言葉になります。認知機能障害が認知症に共通して起こる症状であるのに対し、行動・心理症状(BPSD)は必ず出現するものではありません。

行動・心理症状(BPSD)はなぜ出現するのか?
行動・心理症状(BPSD)のメカニズムを簡単に説明すると、①脳の障害によって、②認知機能障害を基盤に、③苦痛などの身体的不調、不安などの心理的ストレスがきっかけとなり、行動・心理症状(BPSD)出現します。
①脳の障害
脳の萎縮や細胞の壊死、血流不良などによって脳に障害が起こります。
②認知機能障害
認知機能障害によって「自分がどこにいるのかわからない」「覚えていないことをやったと言われる」「今までできていたことができない」といったようなことが毎日続くようになり、普通の生活ですら安心して送れない状況になってきます。
認知機能障害と行動・心理症状(BPSD)は密接に関連しています。例えば、物盗られ妄想は記憶障害がベースとなる要因ですし、帰宅要求は判断力の低下や見当識障害がベースで起こると考えられます。
③不安、不快、苦痛、ストレス
行動・心理症状(BPSD)が起こる背景には、身体的不調や環境の変化、不安、不快感などが様々な要因があります。
・身体的要因
便秘、疼痛、かゆみ、不眠、体調不良、空腹、違和感、疲労、脱水、電解質異常、薬物による副作用など
・心理的要因
治療に伴うストレス、不安、怒り、ケア、自尊心の喪失など
・物理的環境要因
リロケーションダメージ(入院、転居、施設入所、転室など)、五感への不快な刺激など
・社会的要因
家族関係、看護・介護者関係、他入居者との関係など
行動・心理症状(BPSD)をどう捉えるか
行動・心理症状(BPSD)は介護する側にとって負担となります。業務に追われると、つい「自分たちが大変だ」という認識にすり替えられてしまうことがあります。しかし、本人が1番辛い状況にあることを忘れてないのが専門職の基本だと考えています。
BPSDはSOSサイン
行動・心理症状(BPSD)を一言で表すならば「SOS」だと思います。
辛い、痛い、苦しい、怖い、信じられない、やって欲しいことはそれではない、助けて欲しいという思いが、行動・心理症状(BPSD)という形で表現されていると考えています。
まとめ









-4-300x200.png)