認知症の人(とくにアルツハイマー型認知症)は中期以降になると入浴を好まなくなることがあります。原因は様々ですが、根底には不安や恐怖があることがほとんどです。病院でも施設でも通所でもよくある場面なのですが、デイサービスが1番この入浴拒否に頭を悩ませているような印象があります。今回はデイサービスと入浴について考えていきたいと思います。
デイサービスにおける入浴
入浴へのニーズは高いが・・・
デイサービスは入浴をするためだけのものではありません。(入浴専門を掲げてるところは別です)。ですが、自宅で入浴できない人も多くデイサービスへの入浴のニーズが高いのが現状です。これが、本人のニーズだと何の問題もないのですが、家族のみのニーズだった場合に問題が起こります。
本人が入浴したくないなら、入浴しなければいいだけの話なのです。しかし、本人が入浴したくなくても、家族が“入浴させてほしい”という希望がある場合が多いのです。そうなると、入浴してほしい(させたい)介護職と、入浴したくない利用者との攻防がはじまるわけです(笑)

“明日再トライ”できないことと“加算”が関係している
週5回とか利用されている人もいるかもしれませんが、週に2〜3回のデイサービス利用が多いと思います。病院や施設だと、「無理なら明日にしよう」という逃げ道がありますが、デイサービスは「明日」の選択肢がないこと、また入浴加算の絡みなどで職員が必死になってしまう現状があります。
入浴拒否が続くと
入浴拒否が続くと、スタッフのなかで入浴拒否のある人というレッテルが貼られていきます。そして毎回デイサービスに来るなり「この人をいかにして入浴させるか」ということにエネルギーが注がれます。手を変え人を変え、どうにかこうにかお風呂場に誘導することを午前中いっぱい繰り返す。
それで失敗に終わったりすると

今日もダメだった・・・ がっかり・・・
とがっくり肩を落とすわけです。
利用者はどう思っているのか
入浴させることができなかったことにガッカリしているスタッフが気づかないところで

今日も気持ちをわかってもらえなかった
とがっくり肩を落としているような気がします
このやりとりがデイサービスの認識をネガティブにする
毎回こんなことが繰り返されたら、利用者はデイサービスをどのように認識されるでしょうか?私の経験上、『デイサービス = お風呂に入るところ』という誤った認識がされてしまいます。この結果、『お風呂が嫌 → デイサービスに行きたくない』という悪循環が生まれます。
デイサービスで提供したいことは何?
でも、デイサービスが提供するものって入浴だけじゃないですよね?デイサービスが提供したいものって何でしょうか?
・楽しい時間を過ごしてもらう
・自宅の外に出て刺激を感じてもらう
・楽しみながら介護予防に取り組んでもらう
・ご家族にゆっくり休んでいただく
・・・etc
本来デイサービスは、その方が少しでも明るく楽しく過ごしてもらうためのお手伝いをする場所だと私は認識しています。入浴はあくまで、そのなかのひとつの手段でしかありません。
まとめ
介護の仕事が好きな人ほど、熱心な人だからこそ、陥りやすい落とし穴があります。もし今、このような悪循環に悩んでいる人は、もう一度、自分たちのデイサービスが提供したいものは何なのかを職員間で考えてみてはいかがでしょうか?









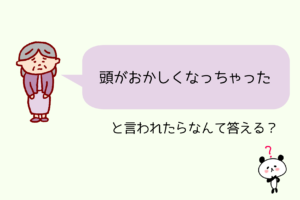











いつも的確なご指摘ありがとうございます。
提供しているサービスの目的は何か?
本質を問う姿勢を大切にします。