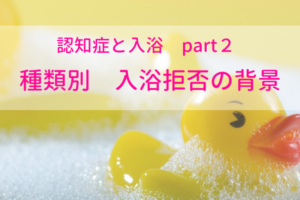こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です
昨日病院の受診だったのですが、半年ぶりに炎症反応が正常値に戻りました。ずーっとこの日を夢見ていた(?)ので、もっと「嬉しいーーーー!!イエーイ!!」ってなるかと思ったけど、めちゃめちゃ低音の小声で「よかった・・・」と呟いただけでした(笑)
上半期は再燃に心身ともにもっていかれた半年だったので、下半期はそのぶんアクティブに活動したいなと思います。
・
さて、今日の記事は失語のひとつである喚語困難がテーマです。
私の勉強まとめノートのようなものです。興味のある方はお付き合いください。
認知症の認知機能障害のひとつに、失語があり、どの認知症のタイプでも失語は出現します
失語と聞くと、全く話せない人をイメージするかもしれませんが、そうではありません
そして失語にはいろいろなタイプがあります

今回のブログでは、アルツハイマー型認知症の言語障害、さらにそのなかの「喚語困難」を読み解いていきましょう。
喚語困難とは
喚語困難は簡単にいうと「言いたい言葉が出てこない」という状態で、呼称障害 とも呼ばれます
いわゆる「あれ、それ」が増えるというやつです

言葉を頭の中に喚起できない状態です
例えば誰かと話をしていて目的の言葉をいうことができない、目の前のものを単語に置き換えることができないなどがこれにあたります
改訂長谷川式評価スケールのなかに、知っている野菜の名前を言ってもらう部分がありますが、これは喚語ができるかどうかもみているようです
人と会話しているとき、大まかにこのように分けることができます
①言葉が聞こえる
②言葉を理解する
↓ それに対する反応として
③目的となる言葉を喚起する
④正しく発音する

喚語困難は③の部分にエラーが起きます
喚語に関わる脳の部位
言語には様々な脳の部位が関わっていますが、喚語に関して言えば
①ブローカ野(三角部・弁蓋部)
②角回(左)
③側頭葉後方下部(左)
が関係が深いことがわかっています

アルツハイマー型認知症の脳の変化
アルツハイマー型認知症の病理変化としては、一般的に海馬~辺縁系が最初に障害を受け、徐々に大脳皮質に病変が広がっていきます
アルツハイマー型認知症では大脳皮質の連合野に障害が強く、前方より後方の方が病変が強いことがわかっていています。

大脳皮質のなかでも、後方帯状回、下頭頂小葉(角回、縁上回)が早期に侵されるらしいです
また側頭葉の後方下部も病変が強いことが知られています


これらのことから、
側頭葉の後方下部・角回などの後方連合野の障害→喚語困難
ということがわかりますよね
ちなみに側頭葉の後方下部は漢字の失書とも関係が深いと言われています。
お役に立つと幸いです
では、またー
【参考文献】
松田実:アルツハイマー型認知症の言語障害の多様性、高次脳機能研究 第 35 巻第 3 号 https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/35/3/35_312/_pdf/-char/ja
大槻美佳著:言語機能の局在地図、高次脳研究、2007 年 27 巻 3 号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/27/3/27_3_231/_pdf
日本認知症学会ホームぺージ
https://square.umin.ac.jp/dementia/link4-1.html