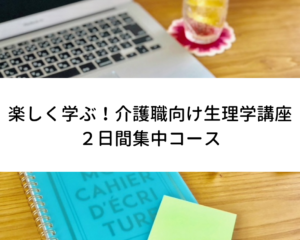2月16日、17日は名古屋・福岡での日総研セミナーでした。
 こちらは名古屋です
こちらは名古屋です
セミナーでたくさんのご質問を頂いたのですが、お答えできなかったものがたくさんありました。とくに名古屋会場では、すぐに福岡に移動しなくてはいけなかったためセミナー終了後に時間を取ることができず、お答えできず、申し訳ありませんでした!
ブログの読書さまのなかにも知りたい方もいると思いますのでこちらのブログにてお答えさせて頂きます!
質問項目が多いので、数回に分けて記事または動画でお答えします。日総研セミナー質問シリーズ(またシリーズだ笑)にしばらくお付き合い下さい。
※当日会場でお答えさせて頂いたご質問は省略させて頂いていますので、ご了承ください

アルツハイマー型認知症の末期の方に筋肉の拘縮が進むケースが多いのは、廃用性以外に何か脳の変化に関係しているのでしょうか?
次のようなことが影響していると考えられます。
①神経細胞の脱落
アルツハイマー型認知症は、アミロイドβたんぱくの蓄積によって神経細胞が死滅し、脳の働きが低下する病気です。神経細胞は、脳からの情報(活動電位)を伝えていく役割があります。神経細胞の死滅により脳から運動の指令が出てもその指令が上手く伝わらなくなるために、運動に障害がでることが考えられます。
もう少し専門的に言うと運動ニューロンが関係しているのではないかと考えられます。運動ニューロンは神経細胞の一種で,骨格筋へ命令を送る機能をもっています。この運動ニューロンの変性などにより筋萎縮や筋力低下が起こるのではないかと考えられます。
運動ニューロンと認知症に関しては、「ALSと認知症」の関係が報告されているようです。
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ninchishou/undou.html
※アミロイド仮説についてはこの質問コーナーが終わったら、記事にします。
②アセチルコリンの減少による平滑筋への刺激の低下
アルツハイマー型認知症では、脳内伝達物質のひとつであるアセチルコリンが減少します。
アセチルコリンの役割のひとつに骨格筋への刺激があるため、アセチルコリンが減少することにより、運動障害がでるのではないかと考えられます。
※脳内伝達物質とは
神経細胞から情報をおくる物資
※平滑筋とは
骨格を動かす筋肉

③運動野の障害
アルツハイマー型認知症では運動に関係する大脳皮質の運動野は、他の脳の部位と比べると保持されるというのが特徴ですが、進行すれば運動野の神経細胞も死滅しますので、運動に障害がでるのだと思います。

まとめ
今日の記事は「生理学的に考えると」という推測の部分も多いので、正しくない点もあると思いますので、参考程度にしていただければと思います。
アミロイドβ、ニューロンなど馴染みのない方にとっては少し難しく感じたかもしれませんね。このような用語も今後「介護職のための生理学」のカテゴリーで詳しく解説していこうと思います。
現在募集中のメニュー

4月11日
羽吹さゆりさんとのトークセミナーです
※こちらは3月21日からのお申し込みとなります。