こんにちは、ブルーベル代表 市村幸美です。
介護職に必要な高齢者の方への基本的な医療知識セミナーで頂いた質問の中から、ブログ記事でも取り上げたいなと思ったものをご紹介していくシリーズです。私個人の見解になりますので、その旨をご了承ください。
今日取り上げるご質問はこちらです。

ご質問ありがとうございます!
改めて「そういえば看護学校で習ったかな?」と思って調べなおしてみましたが、「いつ」は明記されていませんでした。
セミナー中にお答えしたように
安静時(リラックスしているとき)
相手に気づかれないこと
この2つがポイントです。
これもセミナー中に話したような気がしますが、介護現場で私がやっていたのは、利用者さんがフロアでテレビを観ているときに後から測ってました。
本当は胸部や腹部の動きをみて測るのが正しいのですが、集中すれば後ろからでもわかります。
看護学校では、相手に気づかれないように脈拍を測っているフリをして呼吸数を測ると教えられたのですが、なにせポンコツなもので全然できなかった(笑)
視線が挙動不振すぎる・・・苦笑

他のバイタルサイン(体温・脈拍・血圧)と大きく違うのが、自分の意思で回数を変えられるということで、これは呼吸の調節の部分が少し複雑なことが関係しています。
呼吸は延髄の呼吸中枢によって自律的に調整されていますが、大脳皮質にある呼吸筋の調節も絡んでくるからです。

随意と不随意が混在するのが、難しくもあり、からだのすごさでもあります。
すぐに検査ができない介護現場では、利用者をアセスメントする際に呼吸数がひとつの材料となることもあります。
毎日測ることはできないと思いますが、月に1回でもいいので測定をしてその人の標準値を把握しておくといいと思います。
参考になると嬉しいです。
ご質問ありがとうございました!

では、またー






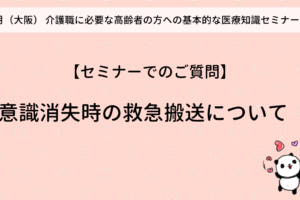


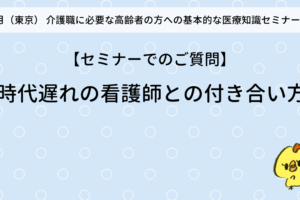

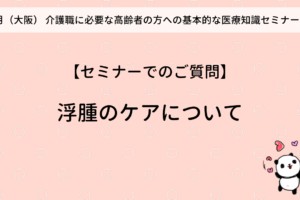








呼吸数はいつ測るのがベストですか?