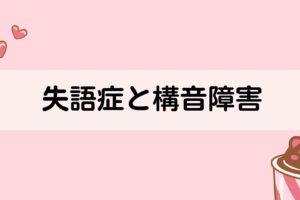こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です。
函館もやっと開花です♡

さてさて、やっと血管性認知症の出番がきました(笑)
では、いってみましょうーーー!
☆参考文献は1番最後の記事にまとめて提示します
・
脳卒中の種類
脳卒中の種類は大まかにこんな感じに分けられます

脳のなかだとこんな感じ

血管性認知症とは
脳の血管障害が原因(脳梗塞・脳出血)
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によっておこる認知症です。
脳卒中になった人が全て認知症になるわけではありません。
アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症のような神経変性疾患とは違い、原因がはっきりしていますね。4大認知症のなかで神経変性疾患じゃないのは血管性認知症だけです。
生活習慣病が関係する
血管性認知症は脳血管障害が原因ですが、脳血管障害の原因は高血圧や糖尿病脂質異常症などの生活習慣病が関係します。
ですので、多くの血管性認知症は予防が可能ともいえます。(血管の先天性異常など生活習慣病とは直接関係ないものもあります)
割合
認知症全体の15%程度を占めます。
え?!少なくない?!と思う人もいるんじゃないでしょうか?
私も看護学校では、アルツハイマー型認知症と血管性認知症が50%ずつと習ったのですが時代は変わりましたね。

症状が人によって異なる
血管性認知症は血管障害の種類や病変の大きさ、場所などによって症状が異なるのが特徴です。
具体的に言えば、脳梗塞なのか脳出血なのか、脳梗塞でもどのタイプなのか、神経細胞が壊死した脳の範囲がどのぐらいなのか、脳のどの場所で血管障害が起こったのか・・・などなどですね。
血管性認知症のタイプ
血管性認知症は次のような種類にわかれています。
| ①多発梗塞性認知症 |
| •大脳皮質を含む広い範囲に比較的大きな脳梗塞が複数発生するタイプ •急激な発症 •脳梗塞が増えるたびに段階的な悪化を示す |
| ②認知症発症に戦略的な部位の単一病変による血管性認知症 |
| •単発の脳梗塞が、認知機能にとって重要な脳の部位に生じることによって認知症が起こるタイプ |
| ③小血管病変性認知症(皮質下血管性認知症) |
| •皮質の下の白質に小さな梗塞が徐々に増えて認知症が起こるタイプ •発症時期がはっきりせず、段階的な悪化も明瞭ではない |
| ④低灌流性認知症 |
| •脳全体の血液の循環が悪くなり認知症が起こる •心停止や高度の血圧低下、太い動脈の高度の狭窄で起こるとされている |
| ⑤脳出血性認知症 |
| •脳出血が原因(脳出血、慢性硬膜下血腫、くも膜下出血など) |
| ⑥その他 |
教科書に出てくるような血管性認知症は①ですね。
今はいろんな研究が進み③が 多いと言われています。
次回はこのなかの①②④⑤について説明して、③はそのあとにじっくり説明します。
では、またーーー