質問コーナー、続いています!ありがとうございます。このコーナーは、一般的な回答ではなく、「私が思う」という視点で答えていきたいと思っています。なのでちょっとひねくれた回答(?)かもしれませんが、読んでいただけたら嬉しいです。

ご質問ありがとうございます!この質問は、過去に幾度となく受けていて、年月とともに私自身の回答も変化してます。。
では、私なりの考えを述べたいと思います。
何もしないのが1番
最初に拒否されたときの対応について答えてしまいます。それは「何もしないこと」です。考えてみれば当たり前のことなんですが、そうはいかないのが認知症ケアの世界です(笑)
それはなぜなのか、考えてみましょう。
なぜ押し切ろうとしてしまうのか?
何もしないことに罪悪感をもつ
おそらくですが、「拒否されたら何もしないほうがいい」と本当は分かっているんだと思います。でも、何もしない=(イコール)何のケアもしていない、と専門職は感じてしまっているのだと思います。何かしなければならない、という強迫観念をもっている専門職は多く、そのようなプロ意識が時として認知症の人を追い詰めているのかもしれません。
どうせ認知症だから、という先入観
そもそも、拒否をされているのになぜそれを押し切ってケアをしようとするのか?なぜできると思っているのか?を考えてほしいと思います。もし、認知症ではない人が拒否をしたらどうしますか?同じように押し切りますか?
もし、「認知症じゃない人にはやらない」ということであれば、どこかに「認知症なんだから、何とかできる」という気持ちがあるのかもしれません。
家族へのアピール
「拒否をされたが自分たちは(自分たちの事業所)はこれだけやった」という家族へのアピールのためにやっている部分も多いと正直感じます。
例えば、デイサービスの連絡帳に
と書くよりも
の方が頑張った感ありますもんね。

何もしないこともケアだと認識する
認知症ケアに限ったことではありませんが、「本人が嫌がることをしない」というのは基本中の基本です。そして、その「本人が嫌がることをしない」というのはケアです。なので、拒否をされたら何もしないことは「何もしない」というケアです。
どうしても、ケアは足し算の思考が強くなってしまいますが、グッとこらえて一歩引くこと、それもケアのひとつです。
「やってあげたい」という気持ちが強い人は、本人の気持ちを押し切って自分が良いと思うケアを押し付けがちです。注意しましょう。
まとめ
「拒否されてもやらなければいけない」と思っていると介護する側も苦しいですよね。拒否されたらやらない、それもケアだと思うことができれば、お互いがもっと楽になりますよ。





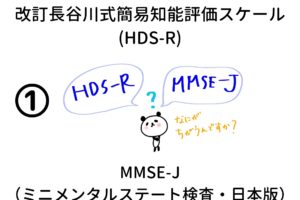
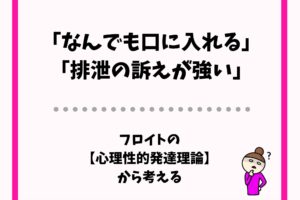













いつもありがとうございます。
大昔のインスタントコーヒーの宣伝文句を思い出しました。
「なにも足さない」♬・・・。
ご家族からすると専門家に任せているから何とか連れ出して。との思いを
肌で感じていろいろ頑張る管理者もおられます。
ご本人の気持ちを大切にすると収益に影響することがちらつくと、
結果として、ご本人・ご家族・事業所・スタッフいずれも笑顔に
慣れない状態になります。
何もしないケア、大いに賛成です。
家族も介護職も「世間体」で動きますからね。
本人の何もしたくないという「自分らしさ」を大事にしてあげれば良いのです。
それが寿命を短くすることに繋がっても。
ご自身の選択が大事です。