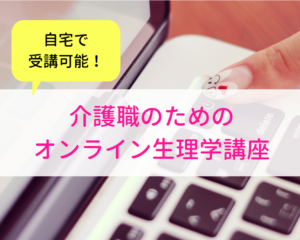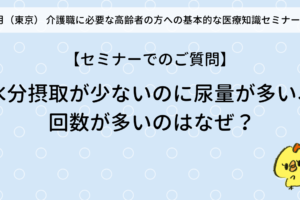こんにちは、ブルーベル代表 市村幸美です。
介護職に必要な高齢者の方への基本的な医療知識セミナーで頂いた質問の中から、ブログ記事でも取り上げたいなと思ったものをご紹介していくシリーズです。私個人の見解になりますので、その旨をご了承ください。
今日は食事中のむせ込みに関する2つのご質問にお答えします。


また、顎が上がりなかなか正しい姿勢を保持できない方への食介のポイントはありますか?
ご質問ありがとうございます!
このご質問からは
①タッピングは有効か?
②むせ込みがない人の誤嚥
について取り上げていこうと思います。
タッピングは有効か?
むせ込みというのは、咳反射のことで、気管に異物が入りそうになったときに外に出そうとする反応です。声帯より肺側は無菌状態ですので、からだは咳を出すことでその無菌状態を守ろうとします。
まず、この基本を整理した上で、タッピングを考えていきましょう。
結論から言うと、タッピッングは現在では推奨されていません。数年前に言語聴覚士さんからお話を聞いた際に、「むせ込みのある人にタッピッングは禁忌ですよ」と言われて、「えーーーーー!!!」とものすごく驚きました。

めっちゃ普通に、なんならいいケアだと思ってトントンやりまくってましたからね 笑
理由は言われてみれば当たり前なのですが、背部を叩くことによって気管→肺に異物が落ちてしまうからなんだそうです。
ムセているときは、タッピングではなく、背中を軽くさすったりして呼吸が整うのをゆっくり待つくらいでいいかと思います。
・
そもそもですが
・むせ込みってなに?
・嚥下ってどういうメカニズム?誤嚥ってなに?
・口から下はどのような構造になっているか?
などを知っておかないと、専門的な視点でケアをするのは難しいかもしれませんね。
むせ込みがない人の誤嚥
先述したように、本来は気管に異物が入るとそれを外に出そうとする反射が起こりますが、その反射が鈍り咳が出ず気管に流れ込んでしまうケースがあります。
経口摂取中の嚥下反射の確認は、甲状軟骨(のどぼとけ)の動きがひとつポイントになってきます。飲み込むときの喉の動きを自分で鏡をみながら確認してみて下さい。
甲状軟骨が上がり、喉の筋肉が収縮するのがわかると思います。それが正常です。「ちゃんと嚥下できているのかな?」と気になる場合は、甲状軟骨の動きを確認してみて下さい。
・
また、不顕性誤嚥と呼ばれる誤嚥もあります。不顕性誤嚥は、睡眠中などに口腔内の細菌が気管に流れ込むことで、それによって誤嚥性肺炎をおこす方もいます。

脳血管障害やパーキンソン病に多くみられます。生理学講座を受けて下さった方はおわかりだと思いますが、ドパミンやサブスタンスPの低下が関係してきます。
健康な人にとってはなんの苦痛もない食事ですが、障害のある方にとっては苦痛で生命のリスクを伴うものでもあるということを知っていきたいですね。
いずれにせよ、口腔ケアは必須です!
次の記事は口腔ケアについての質問を取り上げます。
参考になると嬉しいです。
ご質問ありがとうございました!

では、またー
現在募集中のメニュー
今後のセミナー予定
【東京会場】
10月17日(木)10:00〜15:30
10月18日(金)10:00〜14:30(14:30〜15:30 懇親会)
【大阪会場】
11月 7日(木)10:00〜15:30
11月 8日(金)10:00〜14:30(14:30〜15:30 懇親会)
※募集は8月下旬(または9月上旬)からになります。