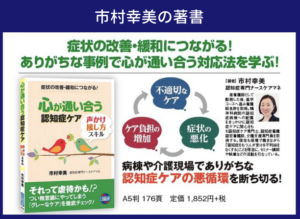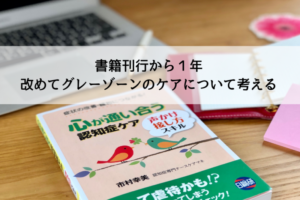3月開催の講座を募集中です!
初の夜コース(2回)です。日中は難しいという方は是非♡
↓

こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です。
今年の確定申告が無事に終わりました。そして気づいたら開業届を出して10年になっていました。サブBLOGにも書いています。
さて、今日の記事は特発性正常圧水頭症(iNPH)についてです。参考書などでは、「治る認知症」としてよく登場するこの病名ですが、よくわからない・・・という方もいらっしゃると思います。
そのような方は参考にしてもらえると嬉しいです♡
・
水頭症とは
髄液が通常より多く頭蓋内に溜まった状態を「水頭症」と言います。
髄液とは
正確には「脳脊髄液」といいますが、省略して「髄液」と呼ばれることが多いので、こちらを使用します。
脳や脊髄は髄液に囲まれて保護されています。髄液に浮いている・・・という感じです。
髄液はくも膜下腔とよばれる部分にあります。脳室とよばれる脳の中の空洞部分で作られ、吸収されながら循環しています。

もうちょっと本格的に書くとこんな感じ。

水頭症の種類
水頭症は下の図のように分類されます。

腫瘍などによって、髄液の交通が障害され髄液が貯留して頭蓋内の圧が上がることを「非交通性水頭症」といいます。
また、くも膜下出血や髄膜炎などで髄液の吸収が障害され髓液が貯留することを「正常圧水頭症(Normal Pressure Hydrocephals:NPH))」と いいます。この場合、髄液の交通は妨げられず、さほど頭蓋内圧が上がりません。
NPHには原因が分からない「特発性正常圧水頭症(iNPH)」とくも膜下出血などが原因で生じる二次的なものがあります。
特発性正常圧水頭症(iNPH)とは
まとめるとiNPHは、原因不明の髄液の異常により脳室が拡大する疾患となります。
そのほかには
・高齢者に多く発症する。好発年齢は70~80歳代
・ゆっくり発症しゆっくり進行する
といった特徴があります。
特発性正常圧水頭症(iNPH)の症状

「歩行障害」「認知機能の低下」「失禁」がiNPHの3大徴候です。

①歩行障害
秒初期からみられるのが歩行障害です。
小刻み歩行、すくみ足、転びやすい、足が重く感じられる、歩行速度の低下、階段使用が困難
②認識機能障害
無関心、自発性の低下などの前頭葉症状を中心に、注意障害などがみられます。
記憶は比較的保たれる傾向にあるようです。

③尿失禁(排尿のコントロールの障害)
頻繁に尿意が起こる、急に尿意が起こる、我慢することができないといった症状がみられます。
タップテスト
診断は頭部MRIやCTなどの画像診断に加え、腰椎穿刺にて髄液を排泄し症状が改善するかをみるタップテストがあります。このタップテストの評価によって治療を検討していきます。
特発性正常圧水頭症(iNPH)の治療
先述したように「外科的手術で治る認知症」として有名な認知症です。治療はシャント手術になります。内服での治療は現在ありません。
シャント手術とは、体内にチューブを留置し脳室内に溜まった髄液を排出する方法です。
簡単にいうと溜まった髄液を他の部分に逃してあげる手術です。
シャント手術の方法は大きく
・脳室と腹腔をつなぐ方法(V-Pシャント)
・脳室と心房をつなぐ方法(V-Aシャント)
・腰椎と腹腔をつなぐ(L-Pシャント)
の3つに分かれ
日本では
・脳室と腹腔をつなぐ方法(V-Pシャント)
・腰椎と腹腔をつなぐ(L-Pシャント)
が多いそうです。

いかがでしたでしょうか?
進行性核上性麻痺などから比べると比較的わかりやすい病態かなと思います。
このあたりは今準備中の認知症ケア講座・中級編で扱っていきますので、楽しみにしていてくださいね!
こちらの講座は認知症の基礎知識がある方が条件となります。認知症ケア講座を受けてくれた方は条件を満たしているので安心してくださいね♡
では、またーーー
3月開催の講座を募集中です!
初の夜コース(2回)です。日中は難しいという方は是非♡
↓

参考文献